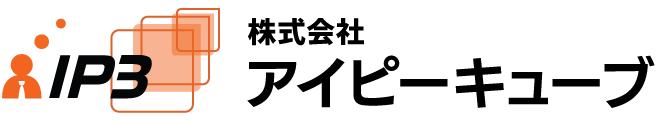なぜ今、ID管理が重要なのか?
クラウド移行、リモートワークの定着、そしてゼロトラストの考え方が広がる中で、企業のIT環境は大きく変化しています。従来のように社内ネットワーク内で完結するセキュリティ対策では、もはや十分とは言えません。「誰が、どこから、何にアクセスしているか」を常に正しく把握し、制御することが求められる時代になっています。
その中心にあるのが「ID管理」です。
ID管理は、企業のセキュリティと業務効率を支える重要な仕組みです。特に、クラウドとオンプレミスが混在する現代のIT環境では、統合的なID管理の導入が不可欠と言っていいでしょう。
アカウント管理の煩雑化
クラウドサービスの導入が進むにつれ、企業が管理すべきアカウントは急増しています。Microsoft 365、Google Workspace、Salesforce、Boxなど、社外からアクセス可能な業務アプリが増える一方で、社内には依然としてオンプレミスの業務システムが稼働しているケースも少なくありません。
このようなハイブリッド環境では、アカウントの登録・変更・削除といった日常的な作業が煩雑になり、属人化やミスの温床となることもあります。
退職者アカウントの残存リスク
組織的なID管理が不十分な環境では、退職者や異動者のアカウントがそのまま残ってしまうケースが少なくありません。たとえば、人事部門が退職を把握していても、IT部門への連携が遅れたために、クラウドサービスのアカウントが数週間放置されていた──そんな事例は決して珍しくありません。
このような「幽霊(ゴースト)アカウント」は、情報漏洩や不正アクセスのリスクを高める重大なセキュリティ課題です。特に、退職者が私物のスマートフォンに業務アプリをインストールしていた場合、退職後も社内データにアクセスできてしまう可能性も考えられます。
ゼロトラストの考え方では、「使われていないアカウントがある」こと自体がリスクと見なされます。こうしたリスクを防ぐには、IDライフサイクル管理の仕組みが不可欠です。
セキュリティインシデント
前述の「退職者アカウントの残存リスク」と同様に、人事部門の管轄外にある利用者アカウント(人事システムに未登録の派遣社員、アルバイト・ベンダー・委託先ユーザーなど)のシステム利用権限の管理不備や削除漏れがインシデントにつながる重大な事例が多数報告されています。
これらのアカウントには、個人の特定が困難な共有アカウントの利用が含まれる場合もあり、付与されたアカウントを踏み台にして高権限アカウントを奪取し、広範囲な攻撃を実行する手口の足がかりとなることがあります。
ID管理において重要なのは、「正しい個人が」「正当な理由で」「適切なリソースに」「最小限の権限で」アクセスできるよう、情報セキュリティとビジネスの両面から運用管理体制を整備・実行することです。
社内統制・監査対応の観点からのID管理
ID管理システムは、セキュリティ対策であると同時に、社内統制の基盤でもあります。誰がどのシステムにアクセスできるのか、いつ・どこで・何を操作したのかを正確に把握できなければ、内部統制や監査対応が困難になります。
また、業務上の責任範囲を明確にするためにも、「誰が何をできるか」をIDベースで管理することは、業務の透明性と信頼性の確保に直結します。
このような背景から、今まさに「ID管理システムの見直しと強化」が求められています。
ID管理(IDM)とは?
IDライフサイクル管理とは?
ID管理(Identity Management、略してIDM)とは、企業や組織におけるユーザーIDおよび関連するアカウント情報の登録・変更・削除といった「IDのライフサイクル」を一元的に管理する仕組みです。従業員が入社・入場し、システムの利用を開始する時から、異動・昇進・退職に至るまで、業務に必要なシステムやサービスへのアクセス権限を適切に付与・更新・削除することが求められます。
この「IDのライフサイクル」に基づくアカウント情報の管理が徹底されていないと、アカウントの二重管理や権限の過不足、情報反映の遅延、オペレーションミスによるヒューマンエラー、退職者アカウントの放置などが発生し、セキュリティリスクの増大や業務効率の低下を招く原因となります。
IDのライフサイクルに基づくアカウント情報の管理は、以下のような一連の流れを指します。
登録:入社・入場時に必要なアカウントを作成し、適切な権限を付与
変更:異動や昇進に伴い、部署・役職・権限などの属性を更新
削除:退職時にすべてのアカウントを無効化・削除
この流れを人事システムやActive Directoryなどと連携して自動化することで、運用負荷を大幅に軽減し、セキュリティと統制を両立するのがID管理システムです。
プロビジョニングとデプロビジョニング
プロビジョニングとは、ユーザーが入社・異動した際に、必要なアカウントや権限を自動で割り当てる仕組みです。たとえば、営業部に配属された社員には、CRMやメール、ファイル共有サービスへのアクセス権限を一括で付与します。
デプロビジョニングはその逆で、退職や異動に伴い不要となったアカウントや権限を自動で削除・無効化する仕組みです。これにより、不要なアカウントや権限の残存を防ぎ、情報漏洩リスクを低減できます。
ID管理を実現するための主な連携対象システム
統合的なID管理を実現するには、社内外のシステムとの連携が不可欠です。代表的な連携対象システムにおける考慮しておきたいポイントを以下に示します。
| 連携対象 | 主な認証・アカウント管理 | 管理対象アカウント情報 | 連携・運用上のポイント |
|---|---|---|---|
| Active Directory(AD) | -社内PCログイン -社内システム認証 -アクセス制御(認可)情報の管理 | -ユーザーID・パスワード -ユーザー属性情報 -グループ情報 | -ID管理システムからActive Directoryへのアカウント情報(利用者パスワード含む)の直接連携 -Active Directoryのパスワード変更に連動したID管理システムへのパスワード同期 -Active Directoryリソースを活用するシステム(ファイルサーバー等)の要件を加味したグループ情報の連携 -Microsoft 365やEntra IDとの統合 |
| LDAP | -アプリ認証 -SSO認証 -アクセス制御(認可)情報の管理 | -ユーザーID・パスワード -ユーザー属性情報 -グループ情報 | -ID管理システムからLDAPへのアカウント情報(利用者パスワード含む)の直接連携 -LDAP管理対象リソースを活用するシステム(アプリケーション等)の要件を加味したグループ情報の連携 -シングルサインオン基盤要件の充足(MFA要件含む) |
| 業務システム | -業務システムの認証 -権限管理 | -ユーザーID・パスワード -ユーザー属性情報 -組織・業務グループ情報 | -ID管理システムから業務システムへのアカウント情報(利用者パスワード含む)の連携 -業務システムのDBへの直接連携 -CSVファイルによる連携 -業務システムの要件を加味したアカウント情報の連携 |
| クラウドサービス | -Microsoft 365、Google Workspaceなどクラウドサービスの認証 -アクセス制御(認可)情報の管理 | -ユーザーID・属性情報 -ユーザー属性情報 -グループ情報 -ライセンス情報 | -ID管理システムからクラウドサービスへのアカウント情報(利用者パスワード含む)の連携 -標準プロトコル(SCIM: System for Cross-domain Identity Management)による直接連携 -クラウドサービスの個別APIによる直接連携 -その他の連携方法 |
これらの連携を通じて、ID情報の一元管理とリアルタイムな同期が可能となり、業務の効率化とセキュリティ強化を同時に実現できます。
ID管理システム導入がもたらす価値
セキュリティ強化
クラウドサービスの普及やリモートワークの定着により、企業のIT環境は社内外に広がり、アクセス経路も複雑化しています。こうした環境では、「誰が、どこから、何にアクセスしているか」を正しく把握し、制御することが、セキュリティ対策の基本となります。
ID管理を適切に行うことで、以下のような“見えないリスク”を排除することが可能になります。
- 退職者アカウントの残存を防ぐ
人事システムとID管理システムを連携させることで、退職情報をトリガーにアカウントを自動削除。不要なIDの残存を防ぎ、情報漏洩や不正アクセスのリスクを排除します。 - 権限の過不足を防ぐ
役職や部署に応じた権限テンプレートを活用し、必要なアクセス権限を自動で付与・更新。業務に不要な権限の放置や、必要な権限の未付与による業務停滞を防ぎます。 - SSO・MFAとの連携で多層防御を実現する
ID管理システムは、SSO(シングルサインオン)やMFA(多要素認証)と連携することで、認証の入り口とIDの存在そのものを同時に制御可能となります。退職者のIDが自動削除されれば、SSO経由のアクセスも遮断され、MFAによる本人確認も無効になります。
ゼロトラストの考え方においては、「使われていないアカウントがある」こと自体がリスクとされます。ID管理システムは、こうしたリスクを可視化し、排除するための基盤として、企業のセキュリティ戦略に不可欠な存在です。
業務効率化
ID管理システムの導入は、セキュリティ強化だけでなく、日々の運用業務の効率化にも大きく貢献します。特に、アカウントの登録・変更・削除といった作業は、従業員の入社・異動・退職のたびに発生し、IT部門の負荷を高める要因となっています。
ID管理システムを整備することで、以下のような業務上のムダを排除し、運用効率を大幅に改善できます。
- アカウント作成・変更・削除の自動化
人事システムと連携することで、入社・異動・退職の情報をトリガーに、必要なアカウントや権限を社内システムやクラウドサービスに自動でプロビジョニング/デプロビジョニングし、手作業による登録ミスや対応漏れを防ぎます。 - 申請・承認プロセスによるアカウント・権限管理
人事部門の管轄外にある利用者アカウントの作成・削除、所属組織や役職などの人事情報に関連しないシステム利用権限の付与・剥奪は、申請・承認プロセスを経て、社内システムやクラウドサービスへ適切に反映することができます。 - 属人化の解消と運用負荷の軽減
従来は、特定の担当者が手作業でアカウント管理を行うケースが多く、管理すべきシステムが増えると、対応の遅れや引き継ぎミスが発生しがちでした。統合的なID管理の仕組みを導入することで、運用ルールを標準化し、誰でも対応できる体制を構築できます。 - ユーザー自身によるセルフメンテナンス
パスワードの変更・リセットや自身の属性変更など、簡易な操作をユーザー自身が行えるセルフメンテナンス機能を提供することで、ヘルプデスクへの問い合わせ件数の削減が見込まれます。IT部門の対応工数を減らし、より重要な業務に集中できる環境を整えます。
こうした業務効率化の効果は、実際の導入事例でも確認されています。近畿労働金庫では、権限管理システムとActive Directoryの連携を自動化することで、日々の運用作業が「1時間」から「5分」へと短縮され、管理者の負荷を大幅に削減することに成功しました。
※参考:近畿労働金庫様
このように、ID管理は「セキュリティのための仕組み」であると同時に、「日常業務のムダをなくす運用基盤」としても機能します。
特に、クラウドとオンプレミスが混在する環境では、ID管理の自動化と統一ルールの整備が、運用の安定性と効率性を支える重要な要素となります。
監査・コンプライアンス対応
ID管理は、セキュリティ強化や業務効率化だけでなく、法令遵守や監査対応の観点からも、企業にとって不可欠な仕組みです。
特に、アクセス権限の適正管理やアカウントのライフサイクル管理は、各種制度や基準において「守るべきルール」として明記されており、対応が不十分な場合には、監査指摘・認証不適合・制裁リスクなどの影響を受ける可能性があります。
以下に、ID管理が関係する主な制度・基準と、その位置づけを整理します。
◆ 法的拘束力のある制度
| 名称 | ID管理の位置づけ | 拘束力 | 対象 | 従わない場合のリスク |
| 個人情報保護法(日本) | 技術的安全管理措置として推奨 ※2025年改正案で強化の可能性 | 高 | 個人情報取扱事業者 | 行政指導・命令・罰則・信用失墜 |
|---|---|---|---|---|
| GDPR(EU) | 適切な技術的管理措置の一例としてID管理が含まれる | 高 | EU在住者の個人データを扱う企業 | 最大2,000万ユーロまたは全世界売上高の4%の制裁金 |
| J-SOX (内部統制報告制度) | アクセス権限管理・退職者アカウント削除が監査項目 | 高 | 上場企業 | 内部統制報告書の不適正リスク |
◆ 準法的拘束力のある基準(業界標準・政府基準)
| 名称 | ID管理の位置づけ | 拘束力 | 対象 | 従わない場合のリスク |
| NISC統一基準 | アカウント管理・権限管理の強化が求められる | 中(実質必須) | 政府機関・自治体・委託先 | セキュリティ監査での指摘・改善命令 |
|---|---|---|---|---|
| 医療情報システム安全管理ガイドライン | 退職者アカウントの即時削除・アクセス権限の適正化が推奨 | 中 | 医療機関・薬局・関連ベンダー | 行政指導・信頼性低下・委託停止 |
| 教育情報セキュリティポリシー | クラウド利用時のID管理強化が推奨 | 中 | 教育委員会・公立学校・自治体 | 監査指摘・補助金不利・信頼性低下 |
◆ 国際的な認証・設計指針(任意だが影響力あり)
| 名称 | ID管理の位置づけ | 拘束力 | 対象 | 従わない場合のリスク |
| ISMS(JIS Q 27001) | 有効な管理策として明記 | 中 | ISMS認証取得企業 | 認証審査での不適合・認証停止 |
|---|---|---|---|---|
| ISO/IEC 27001 | 有効な管理策として明記 | 中 | ISMS認証取得企業 | 認証審査での不適合・認証停止 |
| ISO/IEC 24760 | ID管理の設計指針として関与 | 低〜中 | ID管理システム設計者 | アカウント管理不備による事故の可能性 |
このように、ID管理は単なる運用効率化の仕組みにとどまらず、法令遵守・業界信頼性・認証取得の基盤としても重要な役割を担っています。
SSOやMFAと連携した統合的なID管理を実現することで、セキュリティとコンプライアンスの両立が可能となり、企業の信頼性向上にもつながります。
ID管理システム導入時に気を付けるべき課題
課題①:既存環境との統合と運用設計の複雑さ
ID管理システムを導入する際、多くの企業が直面するのが「既存環境との統合」です。
社内にはActive Directory、人事システム、業務アプリ、クラウドサービスなど、異なるIDソースや認証方式が混在しているケースが多く、これらを統合的に管理するには、以下のような設計上の判断と調整が必要になります。
- どのIDを「マスター」として扱うかの方針決定
- ユーザー属性(氏名、所属、役職など)の定義、連携範囲、更新ルール等の整理
- システムごとの連携方式(CSV、LDAP、DB、SCIM、APIなど)への対応
- IDライフサイクル(登録・変更・削除)の自動化設計
さらに、ID管理システムは単なる「アカウントの一元管理」ではなく、人事情報や認証基盤と連携しながら、業務に必要な権限を適切に制御する仕組みです。そのため、導入時には業務部門・IT部門・人事部門など、複数部門をまたいだ要件整理と運用設計が求められます。
課題②:障害時の影響と可用性の確保
ID管理システムは、業務システムを利用するユーザーを識別するために必要な認証情報(IDやパスワードなど)をはじめ、業務システム内でアクセス制御を行うために使われるアカウントの属性情報を管理する基盤であり、ID管理システムが停止、もしくはID管理システムが保持しているデータが損壊すると、たとえば以下のようなリスクが発生します。
- 業務効率の維持・生産性に影響
IDの作成や適正な権限の付与がシステムに対してタイムリーに行えず、ユーザーがシステムを利用できるようになるまでのリードタイムを必要とします(業務の遅延や機会損失)。 - セキュリティリスク
アカウントの無効化や権限変更ができず、不要なアクセス権が残ることで、機密情報が漏洩するリスクが高まります。 - 不正アクセス
MFAやSSO認証基盤などとのアカウント情報連携が正常に行えなくなり、外部からの不正アクセスを招く恐れがあります。
こうしたリスクを防ぐには、冗長構成による自動切り替えや、障害を即時に検知・通知する仕組みが重要です。また、定期的なデータバックアップと復旧手順を整備しておくことで、万が一の障害時にも迅速な対応が可能になります。
課題③:ベンダーのサポート体制と導入後の運用支援
ID管理システムは、導入して終わりではなく、継続的な運用が求められる仕組みです。ユーザーの追加・削除、属性変更、システムの追加・統合など、日々の運用に対応するためには、ベンダーのサポート体制が非常に重要な要素となります。
特に、以下のような導入に関わる支援があるかどうかが、導入後の安定運用を左右します。
- 導入前の技術支援(PoC、アセスメント支援など)
- 導入時の技術支援(設計・構築・連携支援など)
- 導入後の運用支援(問い合わせ対応、トラブルシューティング、アップデート対応など)
- 日本語対応の有無、対応スピード、運用マニュアルの整備状況
海外製のID管理製品では、英語のみのサポートや、時差による対応遅延が課題となるケースもあります。こうした点を踏まえ、自社の運用体制に合ったベンダーを選定することが、導入成功の鍵を握ります。
ID管理システム導入形態の比較(オンプレミス vs クラウド)
ID管理システムの導入には、大きく分けて以下の2つの形態があります。
オンプレミス型
自社のサーバー環境(物理・仮想・クラウド)に統合的なID管理基盤を構築する方式です。Active Directoryや人事システムとの連携がしやすく、社内システムとの親和性が高いのが特徴。カスタマイズ性に優れる一方で、構築・運用には一定のITリソースが必要。
IDaaS(IDentity as a Service)型
クラウド上で提供されるID管理サービスを利用する方式です。導入・運用が容易で、インフラ管理の負担が少ない反面、社内システムとの連携やカスタマイズ性は限定的で、サービス仕様に依存する部分もあります。サブスクリプション形式のため、ユーザー数や機能追加に応じてランニングコストが変動する点にも注意が必要です。
導入形態の比較表
| 比較軸 | オンプレミス型 | クラウド型 |
|---|---|---|
| 初期コスト | 高め(製品ライセンス料・構築費) サーバー環境が必要 | 比較的低コスト(サブスクリプション) |
| ランニングコスト | 安め(製品保守料のみ) サーバー環境の運用が必要 | 月額課金で継続的に発生 ユーザー数増加により高コスト化の可能性あり |
| カスタマイズ性 | 自社要件に応じて柔軟に設計可能 | 限定的(サービス仕様に依存) |
| システム連携 | 社内システムとの親和性が高い クラウドサービスとの連携も可能 | クラウドサービスとの親和性が高い 社内システムとの連携は限定的 |
| 運用負荷 | 自社で運用 システム全体の運用リソースが必要 | サーバー環境の運用はベンダーが対応 ユーザー管理等の運用リソースは必要 |
| セキュリティ制御 | 自社内で完結 | サービスに依存 |
このように、導入形態の選定は「どちらが優れているか」ではなく、自社のIT環境・セキュリティ要件・運用体制に最も適した構成は何かという視点で判断することが重要です。
とはいえ、「自社にとってどちらが適しているのか」を判断するのは簡単ではありません。
そこで、企業のタイプや状況に応じた導入形態の選び方を、以下にケース別で整理しました。
ケース別:こんな企業にはこの導入形態が向いています
| 企業タイプ | おすすめ導入形態 | 理由 |
|---|---|---|
| 社内システムとの連携を重視 | オンプレミス型 | ADや人事システムとの連携がしやすく、既存資産を活用できる |
| クラウドサービス中心の業務環境 | クラウド型(IDaaS) | Google WorkspaceやMicrosoft 365などとの連携が容易 |
| IT部門の人員が限られている中小企業 | クラウド型(IDaaS) | インフラ管理の負担が少なく、導入もスピーディ |
| セキュリティ要件が厳格な業界 (金融・官公庁など) | オンプレミス型 | 自社内での制御が可能で、ポリシーに準拠しやすい |
| 海外拠点やリモートワークが多い企業 | クラウド型(IDaaS)またはオンプレミス型 | クラウド型:拠点ごとの柔軟な運用が可能 オンプレミス型:本社基盤を共用することでコストを抑えられる |
EntryMasterで実現する安全で効率的なID管理
クラウドサービスの普及と、既存のオンプレミスシステムの継続利用により、多くの企業が「ハイブリッド環境」で業務を行っています。このような環境では、ID情報を一元的に管理し、セキュリティと業務効率を両立できるID管理基盤が不可欠です。
EntryMasterは、アイピーキューブが提供するID統合管理ソリューションで、クラウドとオンプレミスの両方に対応したIDライフサイクル管理を実現します。
IDライフサイクル管理と運用効率化
Active Directoryや人事システムと連携し、入社・異動・退職に伴うアカウントの登録・変更・削除を自動化。属人化や手作業によるミスを防ぎ、IT部門の運用負荷を大幅に軽減します。セルフメンテナンス機能も備えており、ユーザー自身によるパスワードリセットや属性変更も可能です。
高可用性と監査対応
LDAPベースのディレクトリ構成により、検索性・拡張性に優れた高可用性設計を実現。証跡管理やログ管理機能も備えており、監査対応や障害発生時の復旧にも強みがあります。
柔軟な連携と統合認証基盤の構築
CSV・LDAP・DB・SCIM・APIなど多様な連携方式に対応し、既存のADや人事システムとの統合もスムーズ。さらに、CloudLink(SSO)やAuthWay(MFA)と連携することで、ID統合管理・認証・多要素認証を統合した認証基盤を構築可能。ゼロトラストセキュリティの実現にも貢献します。
導入事例と実績
EntryMasterは、製造業、金融、教育、医療など、さまざまな業界で導入されており、セキュリティ強化と業務効率化の両立を実現しています。
アイピーキューブなら、統合認証に特化した専門ベンダーとしての豊富な知識と実績を活かし、柔軟な構成と多様な認証方式で、貴社の課題に最適な解決策をご提案します。
ID管理システム導入に関するご相談はこちら
- 自社に最適な認証方式を知りたい
- クラウドとオンプレミスの混在環境に対応したい
- ID管理システムをMFAやSSOを統合したい
お寄せいただいたご要望の内容により、最適な資料をお送りいたします。また、WEB会議システムを使用して口頭でのご説明も可能ですのでお気軽にお問合せください。


お送りする資料の例
●製品概要
-製品の特長・構成概要・機能紹介・連携可能システム など
●事例紹介
-選定のポイント など
●価格表
-ライセンス料・年間ソフトウェアサポート料・導入サービス料 など
「*」の欄は必須項目となっておりますので、必ずご記入ください。