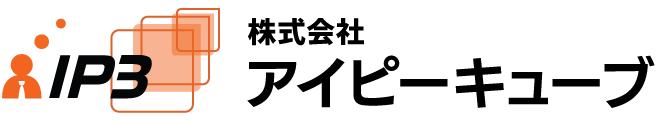なぜ今、SSOが必要なのか?
「パスワード疲れ」という社会現象が生むIT課題とは?
「またパスワードか…」
業務システムにログインするたびに、複雑なパスワードを思い出し、入力する。
このような日常的なストレスは、今や“パスワード疲れ”という言葉で表現されるほど、社会的な課題となっています 。
企業では、クラウドサービスの導入が進み、Microsoft 365、Google Workspace、Salesforce、Boxなど、社外からアクセス可能な業務アプリが急増しています。
一方で、社内にはオンプレミス型の業務システムも依然として稼働しており、クラウドとオンプレミスが混在した環境が一般化しています。
このような混在環境では、ユーザーは複数のシステムに対して個別のID・パスワードを管理する必要があり、ログインの煩雑さが日常的な業務の妨げとなります。
その結果、利便性を優先するあまり、パスワードの使い回しや簡易設定、メモ書きによる管理など、パスワード管理の質が低下し、セキュリティリスクが増大するという悪循環が生まれています。
増大する認証リスクとその背景
こうした状況は、単なる不便さにとどまらず、以下のような重大なセキュリティリスクを引き起こします。
- パスワードの使い回しによるリスト型攻撃のリスク
- 簡易なパスワード設定による辞書攻撃のリスク
- アカウント情報の共有やメモ書きによる不正アクセスによる情報漏えいリスク
これらのリスクは、ユーザーの利便性を犠牲にした結果として生じるものであり、企業の情報資産を守るためには、根本的な対策が必要です。
SSOは「利便性」と「セキュリティ」を両立する鍵
このような背景から、SSO(シングルサインオン)システムの導入が、注目されています。
SSOは、ユーザーが一度ログインするだけで、複数の業務システムにアクセスできる仕組みであり、さまざまなメリットがあります。
- ログイン回数の削減による業務効率の向上
- パスワード管理の簡素化によるユーザー負担の軽減
- 認証情報の一元管理によるセキュリティ強化
ただ、一方で、SSOで利用しているパスワードの漏洩により、複数のシステムにアクセスされてしまうリスクも伴います。多要素認証(MFA)と組み合わせたSSO製品を活用することで、利便性とセキュリティの両立が可能となり、ゼロトラストセキュリティの実現にも貢献します。
シングルサインオン(SSO)とは?
SSOの仕組み
SSO(シングルサインオン)とは、一度のログインで複数のシステムにアクセスできる認証方式です。
ユーザーは、最初のログイン時に認証を済ませることで、以降は追加の認証なしに、社内外の業務アプリにシームレスにアクセスできます。
この仕組みにより、ログイン回数の削減やパスワード管理の簡素化が可能となり、業務効率と利便性の向上が期待できます。また、MFAと組み合わせることで、より強固なセキュリティを実現することが可能です。
SSOの実現方式とは?
SSOを実現するためには、いくつかの技術方式があります。
それぞれの方式には得意な領域があり、クラウドサービス向け・オンプレミス向け・レガシーシステム向けなど、用途に応じて使い分けることが重要です。
多くのSSO製品では、これらの方式を単独ではなく組み合わせて採用することで、クラウドとオンプレミスが混在する環境でも、柔軟で強固な認証基盤を構築しています。
以下に、代表的な4つの方式を比較してご紹介します。
| 方式 | 概要 | 対象システム | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|---|
| フェデレーション方式 | SAMLやOIDCなどの標準プロトコルで認証情報を連携 | クラウドサービス(Microsoft 365、Google Workspaceなど) オンプレミスWebアプリ | 標準プロトコルによるセキュアな方式 クラウドサービスのSSOに適している | SAMLやOIDCに対応していないシステムには適用できない |
| リバースプロキシ方式 (代理認証方式) | プロキシサーバーが通信の中継と認証を制御 | オンプレミスWebアプリ クラウドサービス | 対象システム側の改修が不要 SAMLやOIDCに対応していないWebアプリやクラウドサービスに適している | リバースプロキシサーバーへの負荷集中 ネットワーク構成変更が必要 |
| エージェント方式 | 各業務システムに認証モジュールを組み込む | オンプレミスWebアプリ | 対象システム側での柔軟な制御 SAMLやOIDCに対応していないWebアプリに適している | 対象システム側の改修が必要になることがある |
| クライアント 代行認証方式 | クライアント端末側に導入したSSOソフトウェアがユーザーの代わりに認証情報を代行入力する | レガシーシステム、 オンプレミスWebアプリ クラウドサービス | 対象システム側の改修が不要 レガシーなクライアント/サーバーシステムのSSOに適している | 対象システム側でのログイン画面等の変更の都度、全端末への反映が必要 全端末にSSOソフトウェアの導入が必要 認証情報の保持に注意が必要 |
シングルサインオンの各方式について詳しく知りたい方は、こちらのガイドもぜひご覧ください。
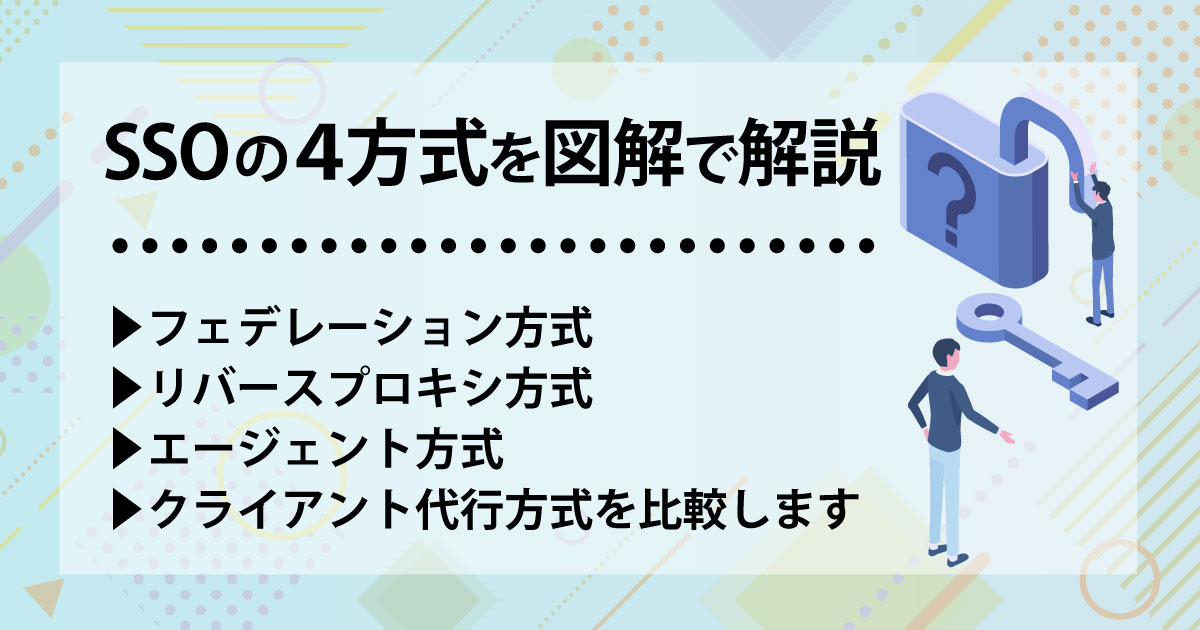
SSOとID統合管理の違い
SSOとID統合管理は、どちらも「複数のシステムと連携し、効率的に管理・利用するための仕組み」ですが、連携する情報の種類と目的が異なります。
| 項目 | SSO | ID統合管理 |
|---|---|---|
| 目的 | 認証の一元化 (認証情報を連携し、ログイン回数を削減) | ID情報の統合管理 (ユーザー情報の連携) |
| 主な技術 | SAML、OIDCなどの標準プロトコル MFAなどの認証技術 | ID情報のプロビジョニング SCIM、LDAPなどの標準プロトコル |
| 利点 | 1度のログインで複数システムにアクセス ユーザーの利便性の向上 セキュリティ強化 | 複数システムのID情報を一元管理運用負荷の軽減 セキュリティ強化 |
SSOは「一度のログインで複数のシステムにアクセスできる」仕組みであり、ユーザーの利便性を高めることが主な目的です。
一方、ID統合管理は「異なるシステム間でユーザー情報を共有・同期する」ことで、ID管理の効率化を図るものです。
両者は補完関係にあり、SSOで認証を統合し、ID統合管理でユーザー情報を統合することで、より強固で効率的な認証・ID管理基盤を構築することが可能です。
SSO導入がもたらす価値
ユーザー利便性の向上
SSOの導入によって、ユーザーのログイン体験は大きく変わります。
従来は、業務アプリごとに異なるID・パスワードを入力する必要があり、ログインのたびに作業が中断されていました。
SSOを導入することで、以下のような具体的な改善が期待できます。
- 1日あたりのログイン回数が大幅に削減され、業務の中断が減少
- パスワードの記憶・管理からの解放により、心理的ストレスが軽減
- リモートワークやモバイルアクセスでも一貫した認証体験を提供
たとえば、クラウドサービス(Microsoft 365、Box、Salesforceなど)と社内のオンプレミスシステムをまたいでSSOを実現すれば、ユーザーは場所や端末を問わず、スムーズに業務を開始できます。
実際、近畿大学では、約10万ユーザーが利用する共通認証基盤において、CloudLinkとAuthWayを組み合わせたSSOとMFAを導入。教職員のほぼ100%がワンタイムパスワードによる二段階認証に移行し、パスキー(FIDO2)によるパスワードレス認証も実現しています。
学内外の複数システムへのアクセスが一度の認証で可能となったことで、授業準備や業務開始時のログイン作業が簡素化され、ユーザーが“何をするか”に集中できる環境が整備されました。
認証の煩雑さを排除することで、業務や学習の流れを止めない“体験設計”を実現しています。
※参考:近畿大学様 導入事例
このように、SSOは単なる「ログインの簡略化」ではなく、業務全体の流れを止めない“体験設計”の一部として、ユーザーの生産性向上に貢献します。
セキュリティ強化
SSOは利便性を高めるだけでなく、セキュリティ対策としても有効です。
特に、以下のような観点で企業の情報資産を守る仕組みとして機能します。
- パスワードの使い回しを防止:SSOにより、ユーザーは1つの強固な認証情報だけを管理すればよくなり、複数のシステムで同じパスワードを使い回すリスクを低減できます。
- MFAとの連携による多層防御:SSOとMFAを組み合わせることで、ログイン時の本人確認を強化し、不正アクセスやなりすましを防止します。
- 認証情報の一元管理:認証の入り口を一本化することで、アクセス制御やログ監査がしやすくなり、セキュリティポリシーの徹底が可能になります。
特に、ゼロトラストセキュリティの考え方においては、「すべてのアクセスを検証する」ことが前提となるため、SSOとMFAの連携はその実現に不可欠な要素です。
運用負荷の軽減
SSOの導入は、IT部門の認証関連業務における運用負荷を大きく軽減します。
- パスワードリセット対応の削減:複数のシステムで個別にパスワードを管理する必要がなくなるため、「パスワードを忘れた」という問い合わせが激減します。SSOにより、ユーザーは1つの認証情報だけを覚えていればよくなるためです。
- 認証ポリシーの統一:SSOを通じて、クラウド・オンプレミス問わず一貫した認証ポリシーを適用できるため、設定ミスや運用のばらつきを防ぎやすくなります。
- トラブル対応の簡素化:認証の入り口が統一されることで、ログイントラブルの原因特定や対応が迅速になり、ヘルプデスクの負荷も軽減されます。
さらに、ID統合管理システムとの連携で、SSOの効果はより高まります。特に、複数のクラウドサービスやオンプレミスシステムが混在する環境では、SSOによる認証統合とID統合管理によるID情報の自動連携が、運用の安定性とセキュリティポリシーの徹底を支える重要な要素となります。
SSO導入の際に気を付けるべき課題
課題①:既存環境との統合と運用の複雑さ
SSOを導入する際、多くの企業が直面するのが「既存環境との統合」です。
社内にはActive Directory、業務アプリ、クラウドサービスなど、異なる認証方式やID情報が混在しているケースが多く、これらをSSOに統合するには、以下のような設計上の工夫が必要です。
- どのIDを「マスター」として扱うかの方針決定
- ユーザーの認証情報や認証ポリシーの整理
- システムごとの認証方式の違いへの対応(SAML、OIDC、LDAP、独自方式など)
また、SSOは単なる「ログインの簡略化」ではなく、認証の入り口を一本化する仕組みであるため、障害時の影響やセキュリティポリシーの整合性など、要件定義や設計の段階で慎重な検討が求められます。
課題②:障害時の影響と可用性の確保
SSOは利便性が高い反面、認証基盤が単一化されることによるリスクも存在します。
SSOサーバーやリバースプロキシサーバーに障害が発生した場合、すべての業務システムへのアクセスが停止する可能性があるため、以下のような対策が重要です。
- 冗長構成(クラスタリング、フェイルオーバー)の設計
- 障害時の代替認証手段の用意(バックアップログイン)
- 障害検知・通知の仕組みと復旧手順の整備
課題③:ベンダーのサポート体制と導入後の運用支援
SSOは導入後も継続的な運用が必要な仕組みです。
ユーザー追加・削除、ポリシー変更、システム追加など、日々の運用に対応するためには、ベンダーのサポート体制が非常に重要な要素となります。
- 導入前の技術支援(PoC、アセスメント支援など)
- 導入時の技術支援(設計・導入支援など)
- 導入後の問い合わせ対応・トラブルシューティング
- 日本語対応の有無、対応スピード、運用マニュアルの整備
特に、海外製のSSO製品では、英語でしかサポートを受けられないといったことや、時差による対応遅延といったことが課題となることもあります。
そのため、自社の運用体制に合ったベンダー選定が、導入成功の鍵を握ります。
SSO導入形態の比較(オンプレミス vs クラウド)
SSOの導入には、大きく分けて以下の2つの形態があります。
- オンプレミス型
自社のサーバー環境(物理サーバー、仮想サーバー、クラウド)にSSO基盤を構築する方式。Active DirectoryやLDAPと連携し、社内システムとの親和性が高い。カスタマイズ性に優れるが、自社での構築・運用が必要。 - IDaaS(IDentity as a Service)型
クラウド上で提供されるSSOサービス。導入・運用は容易だが、カスタマイズは限定的で、サブスクリプション形式のためランニング費用が大きくなることもある。
それぞれの形態は、導入コスト、運用体制、セキュリティポリシーへの適合性などに違いがあり、企業のIT戦略に応じた選定が求められます。
導入形態の比較表
| 比較軸 | オンプレミス型 | クラウド型(IDaaS) |
|---|---|---|
| 初期コスト | 高め(製品ライセンス料・構築費) サーバー環境が必要 | 比較的低コスト(サブスクリプション) |
| ランニングコスト | 安め(製品保守料のみ) サーバー環境の運用が必要 | 月額課金で継続的に発生 ユーザー数増加により高コスト化の可能性あり |
| カスタマイズ性 | 自社要件に応じて柔軟に設計可能 | 限定的(サービス仕様に依存) |
| システム連携 | 社内システムとの親和性が高い クラウドサービスとの連携も可能 | クラウドサービスとの親和性が高い 社内システムとの連携は限定的 |
| 運用負荷 | 自社で運用 システム全体の運用リソースが必要 | サーバー環境の運用はベンダーが対応 ユーザー管理等の運用リソースは必要 |
| セキュリティ制御 | 自社内で完結 | サービスに依存 |
導入形態の選定において重要なのは、「どちらが優れているか」ではなく、自社の業務環境やセキュリティ方針、ITリソースの状況に最も適した構成を見極めることです。
SSOは、単なるログインの簡略化ではなく、認証の統合と運用効率の向上を目的とした基盤整備です。そのため、導入形態の選定を誤ると、利便性やセキュリティだけでなく、将来的な拡張性や運用負荷にも影響を及ぼす可能性があります。
そこで、導入の方向性に迷った際の参考として、企業の規模や業務特性に応じた導入形態の選び方を以下に整理しました。
ケース別:こんな企業にはこの導入形態が向いています
| 企業タイプ | おすすめ導入形態 | 理由 |
|---|---|---|
| 社内システムのSSOを重視 | オンプレミス型 | ADやLDAPとの連携がしやすく、社内システムとの親和性が高い |
| クラウドサービスとのSSOを重視 | クラウド型(IDaaS) | SAML/OIDCなど標準プロトコルによる連携が中心で、連携済のクラウドサービスも多い |
| IT部門の人員が限られている中小企業 | クラウド型(IDaaS) | 導入が簡単で、インフラ管理の負担が少ない |
| セキュリティ要件が厳格な業界 (金融・官公庁など) | オンプレミス型 | 自社内での制御が可能で、自社ポリシーに準拠しやすく、カスタマイズ性も高い |
| 海外拠点やリモートワークが多い企業 | クラウド型(IDaaS) or オンプレミス型 | クラウド型:各拠点でサポートが受けられる オンプレミス型:本社に導入したSSO基盤を共同利用することで、コストが抑えられる |
| 既存のADや社内ID管理システムを活用したい企業 | オンプレミス型 | ID統合や段階的な導入がしやすい |
アイピーキューブでは、オンプレミスとクラウドの両方に対応したSSO製品であるCloudLinkを提供しています。
CloudLinkで実現するハイブリッド環境のSSO
ハイブリッド環境のSSOをCloudLinkで実現
クラウドサービスの普及と、既存のオンプレミスシステムの継続利用により、多くの企業が「ハイブリッド環境」で業務を行っています。このような環境では、クラウドとオンプレミスの両方に対応したSSO基盤が不可欠です。
CloudLinkは、アイピーキューブが提供するSSOソリューションで、オンプレミス環境とクラウドサービスの両方の認証統合を実現します。Active Directoryとの連携や、SAML/OIDCなどの標準プロトコルに対応しており、Microsoft 365、Google Workspace、Salesforceなどのクラウドサービスと、社内業務システムの両方を一元的に認証管理できます。
CloudLinkを導入することで、ユーザーは一度のログインで複数の業務システムやクラウドサービスにアクセス可能となり、ログイン体験の向上と運用効率の改善を同時に実現できます。ー属性やアクセス環境に応じた柔軟なMFA構成が可能です。

CloudLink CloudLinkはGoogle Workspace/Salesforce/Microsoft 365等のクラウドサービスや企業内Webサイトとのシングルサインオン機能を提供します。
MFAやパスキー認証も同時に実現
CloudLinkは、同じくアイピーキューブが提供するMFAソリューション「AuthWay」と連携することで、SSOと多要素認証を統合した認証基盤を構築できます。
AuthWayは、以下のような認証方式に対応しており、CloudLinkと組み合わせることで、より強固なセキュリティを実現します。
- OTP(ワンタイムパスワード)
- プッシュ通知による二経路認証
- パスキー(FIDO2)によるパスワードレス認証
この連携により、SSOの利便性とMFAのセキュリティを両立し、ゼロトラストセキュリティの実現にも貢献します。
導入事例と実績
CloudLinkは、製造業、金融、教育、医療など、さまざまな業界で導入されており、セキュリティ強化と業務効率化の両立を実現しています。
-

株式会社イシダ 様
Microsoft 365をはじめとするSaaS向け認証基盤をIP3-ACEで構築 「いつでもどこでもどんなデバイスからでも、安全に使える環境づくり」に成功。 -



学校法人近畿大学 様
2段階認証/シングルサインオンシステムへ「FIDO認証」を追加導入、全学約4万5千人が使う共通認証システムの「利便性」が大きく向上。 -



学校法人近畿大学 様
ワンタイムパスワードを利用した2段階認証を導入し、不正ログイン対策について本格的に取り組む。西日本最大規模の総合大学が、全学約4万7千人を対象にサービスを開始。 -


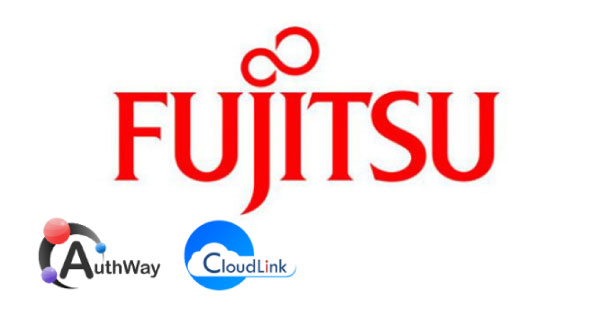
富士通株式会社 様
富士通は、アイピーキューブの製品とシステムインテグレーション支援で新規クラウドサービス認証基盤のスピード開発に成功。 -



日本システムウエア株式会社 様
クラウドサービス/オンプレシステムの双方をシームレスに連携。統合ID管理・SSO・多要素認証を備えた画期的なIDaaSを提供開始。
CloudLinkは、オンプレミスからクラウドまで、ハイブリッド環境のSSO基盤を提供し、セキュリティ・利便性・運用効率のすべてを高いレベルで実現する認証ソリューションです。
Active Directoryとの連携やSAML/OIDC対応により、既存の社内資産を活かしながら、クラウドサービスとの認証統合をスムーズに実現。さらに、AuthWayとの連携により、MFAやパスキー認証を組み合わせた統合認証基盤の構築も可能です。社内外のシステムを一元的に認証管理したいとお考えの方は、ぜひご相談ください。
SSO導入に関するご相談はこちら
- 自社に最適な認証方式を知りたい
- クラウドとオンプレミスの混在環境に対応したい
- MFAとSSOを統合したい
お寄せいただいたご要望の内容により、最適な資料をお送りいたします。また、WEB会議システムを使用して口頭でのご説明も可能ですのでお気軽にお問合せください。


お送りする資料の例
●製品概要
-製品の特長・構成概要・機能紹介・連携可能システム など
●事例紹介
-選定のポイント など
●価格表
-ライセンス料・年間ソフトウェアサポート料・導入サービス料 など
「*」の欄は必須項目となっておりますので、必ずご記入ください。